白馬を見たか1 [AtBL再録2]
![]()
真夜中の幹道を白い馬が走ってゆく。
銃剣を帯びた兵士たちを乗せたジープがそれを追う。嘲弄の銃弾を散発的に浴せながら。戒厳令下の深夜である。
いうまでもなく、コスタ=ガブラスの『ミッシング』の一場面であるが、わたしは、これほど見事な革命と反革命の配図を、かつて見たことがなかった。それは、一瞬よぎった幻影とすますには少し長く、気恥かしい感動に胸を熱くさせるには、少し短い、一場面だった。
端的にいえば、一九八二年の映画を語るためには、この場面だけでよい。他は面倒だ。こう思うのは一瞬のため息のようなものだ。ため息であるためには少しばかり長いものを、書かねばならないのだが。
今年は『レッズ』で始まり、『1900年』で終った、といっていいかもしれない。わたしに関しては。
共に、長く、退屈で、ウスラデカイだけの映画であった。文句のつけようのないのは、両作品の撮影監督であるヴィトリオ・ストラーロの素晴らしさのみである。
このカメラワークを前にして、浴々たる自然の雄大なたたずまいがくりひろげる大絵巻に、ただただ感服する他ない。今世紀の歴史叙事詩が、このような壮大な美しさに定着されたことには、素直に感動するべきだろう。けれど、こうした限定評価は、例えば、デ・パーマのいかにも下らない『ミッドナイト・クロス』はヴィルモス・ジグムントのカメラのみに支えられて秀逸であった式に、いくらでもいい得るから、もうやめよう。全く下らないのだ。
『レッズ』は、ハリウッド式のラヴ・ストーリーで、これまであまり脚光を浴びなかった歴史上の人物を身近に「解釈」した安直さだし、『1900年』は、すべてを二分法に、ファシストとコミュニスト、地主と小作人、男と女、田園と都会、といったふうに図式化した俗悪さなのである。共に二〇世紀の革命は如何に、今日、映像化しうるかの難問への、かなりげっそりさせる回答である。
二つの大作がそろって、革命は額縁に収納しうると、怒鳴り立てているのである。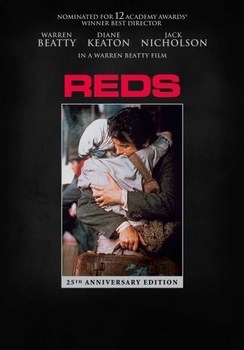

わたしは、これらの映画を、かなり満員に近いロードショーの映画館で見た。映画芸術の総合性の要素の一つとして、観客全体が形作るアトモスフィアを数えたいから、窮乏する余暇と娯楽費用とをさいて映画館に入場する観客たることが、一等、正当な映画の見方だと思う。こんなことを、とりわけ考えたのは、『レッズ』の第一部のクライマックスが、ちょうど十月革命の勝利に置かれていて、そこに高らかにインタナショナルの歌声が流れた時のことなのである。わたしは、確かに、いくつかのすすり泣きをきいたのであった。
まいったね。
やはり泣かせ場というのはあって、これがうまくいけば、観客は手もなく一体化する。わたしは、幼少の頃、『喜びも悲しみも幾年月』という映画(『私は貝になりたい』でもいいか)を見た時のことを想い出してしまった。あの時は、本当に、劇場全体が一つになって、泣いていたような記憶がある。それとはまた違う。明らかに違う泣きようなのだった。
もらい泣きはしなかったが、ハリウッド映画が実現した「革命スペクタクル」が、現代史の中の左翼ノスタルジアの源泉に、どたどたと土足で上り込んできたことに唖然としてしまったのだ。こうした、映画の総合的な侵犯性を、その総合性から外して読み誤ると、映画批評は、じつに悲惨なポンチ絵を描くことになる。例えばこれ。
《第一部の終わり、インタナショナルの高鳴と共にロシア革命の詩と真実が、あくまで史実に正確に再現されて行くあたりで、私はほとんど涙した。ああ、過ぎ去りし革命の青春よ!》(『シティロード』一九八二年四月号)
松田政男の文章である。
インタナショナルヘのすすり泣く(忍び泣く?)連帯は、かかるネクラヴィチ・陰湿スキーな郷愁に支えられていたのである。こうでしかないのだ。
ジョン・リードの生涯を、ロシア革命との関連において、過大に評価する傾向は、全く無邪気なものだ。リードを論じて、かれとメキシコ革命の関係に、再三、注意をうながしたのは鶴見俊輔だった。リードのメキシコ革命への加担が注目されるべきなのは、かれがそこで革命の現場リポーターとして、『世界を震憾した十日問』に先行する書物を書いた、というような皮相な理由からではない(依然として『叛乱するメキシコ』〔邦訳小川出版〕が絶販なのは残念であるが。――後日、筑摩書房から再刊された)。リードがメキシコに潜入する一九一三年は、かれのラディカリストとしての出立においても、また米国のラディカリズムの昂揚においても、一つの明瞭なメルクマールを作っていた。いわば、二十世紀米国史の華であり、そこに自らの青春を同化したリードらの頂上なのである。
映画は、そういうおいしいところを、一切、投げ棄てて顧りみなかった。一種の外食産業の方法である。しかし、その時期を抜きにしてリードの半生を内面的に脈絡付けることなど、出来はしないのだ。道具の豪華さでごまかす恋愛映画に終始してしまった理由はここにある。
『レッズ』が、歴史観などという代物からは、はるか彼方にパープリンであるのに較べれば、ベルトリッチの『1900年』は、まがりなりにもそれらしきものをもっている。
例の二分法という素晴らしく切れ昧の良いやつを。わたしは、この映画の長々しい長尺の必要性をどうにか感得しえた者だが、それ以上に、前作の『ラスト・タンゴ・イン・パリ』や『暗殺のオペラ』でよく了解しえなかった部分が、やっと解けたというおまけまで得た。
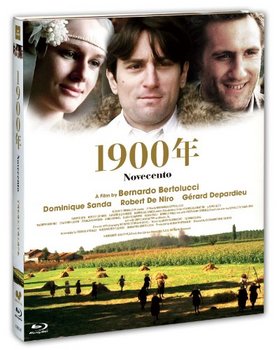
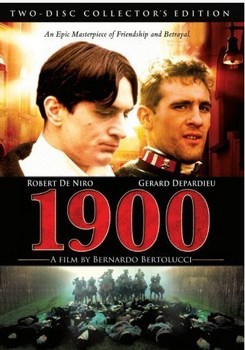

『1900年』は、ベルトリッチ映画の集大成であり、かれのすべてであろう。ここには、『ラスト・タンゴ――』のものうい没落前夜的な刹那のダンスの交感もあれば、『暗殺のオペラ』の探究する者が歴史のクレバスに落ち込んで踏み迷い逆に探究される者に変るという廻り舞台もある。
そう認めた上で、次のように断定できる。ベルトリッチは正真正銘のアホである、と。
作者が、北イタリアの自然への豊かな愛情を、彼女を主人公とすることで、報いたかったことは非常によくわかるし、今世紀前半の激動の転変を、おおどかに横たわる四季物語の推移のうちに捉えてみたいと欲求されたときに、この映画の「話題」の大河的時間が必然的だったこともよくわかる。ただここでは、歴史的存在たる人間が主人公ではないのだ。
ベルトリッチは、歴史を描きえない自らの感性の質にもっと謙虚であるべきだった。かれの描くものは静物画である。かれの人物は人間のようには踊らない。永遠の輪廻に振り付けられた二種類の人形のようにしか踊らない。こうした図柄の中では、赤旗を林立させた列車はどんな時代にも気ままに走っているし、エミリア平原とボー川の朝はいつも一九四五年四月の「解放」の朝かもしれないのだ。
つづく






Stendra For Sale Without Dr Approval <a href=http://purchasecial.com>п»їcialis</a> Comparatif Clomid
by StevSwitte (2019-05-11 05:26)