略奪された映画のために モ一ニングテイク2 [AtBL再録2]
略奪された映画のために モ一ニングテイク2 つづき 山岡強一『山谷』
風景は涙をもて奪い返えせ。
朽ち果てた像を自らの姿として決起せよ。
むしろ山岡は映像を撮りに筑豊行をしたのではなく、寄せ場闘争における自らのスタンスを確認するために、その証拠を筑豊で見つけ出してきたのではないか。そう思わせるところがある。オルガナイザーのしたかかな計算といえるが、この正当さは全く疑いえない。

映画のこの部分のうつくしさとたたずまいのいさぎよさには正当性がある。映像が運動の具体的な提起として立ち上がることは何も偶然ではない。
寄せ場は単独に寄せられたのではない。
そもそもこの帝国近代現代史において、単独に寄せられる場所などない。ありえない。だから風景とは必然である。この帝国主義において必然でないことなどいっさい何もない。
寄せ場プロレタリアートは歴史的にいっても現在的にいっても、単独にそのものであることはできない。ただ単純にそれはできないのである。資本の暴虐がいかに巧妙に分断を策し、個々を引き裂こうとも、一人は単独者であることはできない。これは古典的な命題として絶対にそうなのである。そうであるほかないのである。
かれらは強制連行された朝鮮人・中国人と全く正当につながってくる。それが歴史だった。
しかし映画『山谷』がそのことを説明するわけではない。ラスト近くの暗い玄海灘は全く無雑作に映し出される。それは正当なのだろうか。画面をいったんは受け入れなければ映画を消化することはできない。素朴にいって、ここでも、映画『山谷』は難解さを増している。この画面の質量を受け止めることは、ある意味では困難かもしれない。
一つの想像力の質と日本近代史の一定の予備知識が要求される。
大体、全篇にわたってそうなのだ、ともいえるのだが。
歴史は映画の中で充分に説明を与えられてはいない。もともと映画は近代史の祖述のためのものではないから、映画の外に在る他ない。
海も墓標も、単独には、画面として、単に海や墓標であるにすぎない。観る者の想像力の受信力によって幻視されもし、まったく看過されもする。
風景、それらは日帝の近現代史が無雑作にばらまいた自らの腫瘍であり、これがかきむしられれば、その傷は奥深く、中枢にまでつながっていくだろう。そう受感する力がなければ、これらの映像は単なる海、単なる風景である他ない。
不注意な観客は映画『山谷』を充分に観てとることができない。
もちろん、日本人一般の歴史意識の低劣さを、たった一本の映画が癒やすべくもないことは、指摘するまでもあるまい。

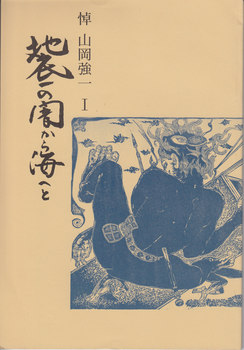
ただ『山谷』に特有なのは、観る者に対して一定の質を要求して止まない、という基本的な姿勢であるといえる。これは映像集団〈山谷〉が最終的に獲得した地平であるに違いない。
映画を観ることが共に観ることであり、共に考えることであるとするなら、一歩すすんで共に創ることでもありうるに違いない。不完全な映像を素材に討論をするという意味ではない。ましてや完全な映像を素材に上からの教宣がなされるというのでもない。
観ることが集団制作の一環、本質的な要素であるような質をかちとっていくこと。映画『山谷』の素朴な難解さは、こうした集団制作の作法に帰せられるようだ。
そうして映画『山谷』は一つの作品で先ずあることができずに、〈映画=運動〉ともいうべき奇妙な結合物に収束している。これは運動という観点から短絡するなら、映画を一つの道具としてみなすことができ、結構なことになるかもしれない。映画は単なるプロパガンダであればよく、集会場に持ち運ぶカンパニアの手軽な道具になってしまう。たぶんそのように解消されるものについては語らずに済ますことができるだろう。
だから問われるべきは、運動とは切り離された映画作品そのものとしての『山谷』の成立であるかもしれない。困惑すべきことに、こうした切離が不可能なところに作品『山谷』はある。『山谷』は映画ですらないのかもしれない。映画そのものについてだけ語ることが厳密な意味において不可能なのかもしれない。
だからこの映画にとって上映運動とは、作品と一体化した、本質的な方法である他なかった。上映という形によって作品をなおもつくり続けること。上映運動によって作品がより完成=解体に向けて、盛り上がること。完成が解体と重なってくる局面は重要である。
解体とは作品が各個人の中で生き始めることだろうから。
九〇年一月、製作上映委員会は、解散と報告の集いを貫徹して、この五年間の総括を行った。
上映運動は、北海道から沖縄までの国内はもとより、香港、フランス、ドイツまで拡がり、延べ五百ヵ所、五万人の観客をかちとった。
八五年十二月二二日、佐藤満夫の虐殺一年にあたる日に始まる、克明な上映運動のクロニクルは、これ自体、重いメッセージを発信してくる。
『山谷』は単独に映画であることができない。映画という手段は、寄せ場において、最初から彼岸のものだった。カメラはあくまで外にあるものだった。カメラをぶんまわすことはそれを武器とすることではない。略奪された映画があったのではない。あらかじめ略奪された場においてカメラを内側にむけることのできる力量を主体はもちえるだろうか。
ドキュメンタリーのアポリアは、それ自体として、変わらず横たわっていた。
上映運動の初期に、上映委は再度、筑豊を訪れている。上映日程の作製とロケ隊が世話になったことの返礼もかねて、である。この筑豊行の報告ほど映画そのものとわかちがたく結び着いているものはなかった。
それは、映画がとらえた朽ち果てた風景すらもが、その後まもなく消え去っていったことを報告している。壊されていく炭鉱住宅、新しい墓石によってとりのけられていく朝鮮人労務者の墓。
再訪は、映画撮影から半年後のことにすぎない。この崩れ去るスピードに何をいうべきか。だとすれば、映画『山谷』はかろうじて、壊死する風景の最終的な記念碑となる他なかったのである。
これは苦いにがいイロニーであるように思える。それとも映画に撮られることによって奪回されることを怖れた帝国主義の風景が自らをスクラップ化して証拠の隠滅をはかったのか。
そう思わせるような壊死のスピードではなかったか。

上映運動もまた作品の一部であるという深い確認はここにも見い出すことができる。映画はより豊饒に集団化しているのである。上映運動への強固なインパクトが山岡強一の死であったことは疑いえない。またしても負の方向から、運動は飛躍を強いられたのである。
佐藤満夫の戦死の無念を引き継ぐことなしには映画『山谷』は発展させることができなかった。今また、その地平を主要にきりひらいた当事者である山岡強一の戦死が、付け加えられるのである。八六年一月十三目、この無残な日付けは忘れられることができない。
映画がもし、佐藤-山岡という個人リレーの産物であるなら、残された者は感傷の涙でそれを祭り上げる他なかっただろう。死は改変しえない事実だから、映画にとって二人の死がわかちがたいことは、無体なことではなかった。
まだ明けきらない新宿の路上、狙い撃たれた銃弾と流された血の記憶は、『山谷』の撮られることのなかったワン・ショットのように、脳裡から離れ去ることはなかった。
これは映画への決定的に雄弁な注釈ではないだろうか。低度の感傷の次元で、映画は、二人の死、とりわけ山岡の死に決定的に規定されてしまったのである。
かれらの戦死をつきつけられることなしに、映画を見始めることすらできない、という具合に。それをたんに否定することはできない。しかし感傷にとどまることもまた許されない。
そこに上映委の再度の集団化構想があったのだと想像する。
この地上に血ぬられた圧制が消え去ることはない。ユルマズ・ギュネイの『敵』という映画だったか、朝、手配師が労務者たちをトラックに乗り込ませる場面。一人の男が遅れてやってきて、トラックの荷台に跳び乗ろうとするが、失敗して転倒する。男は頭から血を流し、長々と舗道にのびてしまう。いつまでも動かない。
死んでしまったのだ。巡査がきて死亡を確め、新聞紙をかぶせて去ってゆく。やがて雨が降ってきて新聞紙をぬらすが、死体は放置されたまま。夕方になってもそのままだ。
この映像にショックを受けたことがあるが、最近、首都のオフィス街で同様のものを見た。朝のラッシュである、山手線だったか、人身事故があった。電車はこうした事故の通例に反して、止まらなかったのである。死体は取り片付けられ、といってそんな時間はないので、線路の脇に置かれた。とりあえず、である。死体の全部か一部か定かでなかったが、ビニールをかぶせられ、電車を止めるわけにいかないので、放置されたのである。乗客たちは非日常の光景に気付くこともなく……。
この地上に虐殺は終らない。映画『山谷』は終ることを拒否した。
最終のシーンに、インドネシアの教科書から、ロームシャの一語がクローズアッブされる。そしてフィルムは途切れる。
ここで歴史が反転し、フィルムは逆向きに回るのだろうか。あるいは観客一人一人の内部で回り出すのかもしれない。
映画は現実のほうに還される――現実へと解体されるのである。
事実として作品は一定の時間枠に完成しているのだが、それ自体としては終ることができないことを、絶えず観る者に発信している。その未完結を受信しなければ、映画を、本当に観たことにはならない。
寄せ場の歴史の集合に相対することが要求される。どこが入り口であるにしても、根源はここにある。
略奪された映画のために現実が略奪されてこなければ、観るという行為は貫徹されない。
死者をよみがえらせることはできないが、よりよく自らのうちに死者を直立させることは、残った者の責務である。
そうでなければ、映画をめぐる二人の戦死を本当に悼むことはできない。
結果として映画『山谷』すらも取り逃してしまうことになる。
自らを対峙させ、自らのうちに正当に葬ってやることなしには、死者はいつまでも死んだままなのだ。
1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし






コメント 0