足立正生『映画/革命』について [映画VIDEO日誌2001-03]
足立正生『映画/革命』について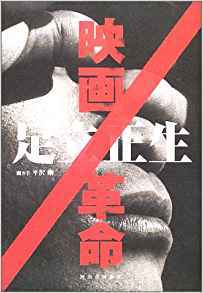
この本は、映画について語られた書物の多くが帯びる悲哀とは無縁だ。
「作家=運動者」という概念を自然体として通過した足立のスタイルには、気負いも挫折感もない。声高なアジテーションもない。驚くほど率直な自己開示がここには満載されている。
あえていえば『映画/革命』は足立という表現者そのものでもある。
表現者は、作家性と運動性とを自在に行き来する。だが運動者の側面に比べて足立の作家性はごく貧しい。
この「貧しい」という認定がわたし自身の観点の貧しさをも露呈することは承知しているが、その上でなお断定を取り下げることはできない。
この本を読みながら、足立の監督作品のいくつかをおぼろげに思い出した。はるか彼方に忘却していたことだ。
『堕胎』や『鎖陰』は京大のバリケードの中で観たのだと思う。
『叛女〈さからめ〉/夢幻地獄』や『噴出祈願/15歳の売春婦』は、新宿まで出てきたときに観た。
『銀河系』や『性遊戯』や『女学生ゲリラ』などは西部講堂で観たはずだ。
それから『赤軍――PFLP・世界戦争宣言』も。
二十代の前半だった。どれも鮮烈に刻まれているとはいいがたい。
初めて観た作品が『堕胎』で、その時の失望と当惑のほうが鮮やかに残っている。
要するに「状況/映画」としてわたしの追憶のうちにしまいこまれているが、作品自体の力としてはささやかな光しか放っていない。作家足立はその程度の重みしか持っていなかった。
ピンク映画であるのにエロがない。他の抽象物は雑多にまぎれこんでいるのにエロだけがない。
ピンク映画に期待される唯一のものが欠けていながら、妙に騒々しく、過度に図式的なのだった。
若松映画のぎとぎとした暗い怨念といった質とは明らかに系統の異なる観念性だった。
そして著書『映画への戦略』に顕著な、政治臭の強い文体。これは著者の本位ではなく刊行されたというが、印象は定まってしまった。新左翼特有の難解さというより、とても血の通った人間が書いたとは信じられないような観念的な作文にがっかりした。だから以降の行動選択にしても、ロマン的な意味以上のものを見い出すことができなかった。

『映画/革命』で足立は自作についても饒舌に語っているけれど、作家の意図したたいていのものをわたしは観落としていると思う。
一般的にいえば、自己解説の必要な作品の価値は低くなる。かえって大島渚や若松孝二の作品分析が優れている。
そしてこのこと自体が足立の不安定な作家性を側面から証明してしまっているように思える。
作家であるより、より運動者であったという意味だ。
運動の意味を、ここでは、「芸術は芸術運動のなかからしか生まれてこない」という花田清輝テーゼに従って使う。
そのテーゼの実践者としての足立は、さして気負いをみせることもなく、テーゼを当たり前の所与のようにふるまっている。その点は見事に一貫して『映画/革命』という書物を緊張させている。
彼が作家性について語るほど、オルガナイザーとしての卓抜さが明瞭になるようだ。ただしそれは自作についてはあまり有効だとは思えない。大島や若松の作品についてなら他の追随を許さない分析がなされているのだが――。
もちろん足立はそこで批評者としてではなく、「批評=運動」者として真価を発揮しているのだ。
この本の全体から受ける足立のイメージは、火野葦平の登場人物のようだ。
しかし抱懐した思想は晦渋さにみちみちている。日本の農民が軍国主義を支えてきたとすれば、足立は同じ血をボリシェヴィズムの芸術運動に捧げた(現在も捧げつつある)といえる。
芸術運動は、悲劇を演ずるか、あるいは無様な笑劇をしか残さないで終わる。――これには、とくにみるべき作品を生み出さなかったケースにおいては、という注釈がつくけれど、じつにしばしば運動は運動の軌跡のみを累々と積み重ねて消尽されていく(から注釈は無用かもしれない)。
表現活動はすべてエゴに回収されてしか現実のものにならないという常識からすれば、それを共同化する作業は想像を超える。芸術運動の理論の難解さは、単純にいえば、いかにその常識から身を引き剥がすことができるかにかかっている。
個人の表現活動を集団的に開示していくという、生理感に反する行為を実現できるかどうかだ。
集団イメージが個人の秘密領域を浸触してくると捉えるかぎり、その理論には近づきえない。「花田・吉本論争」における吉本の世代実感主義のように。
芸術運動理論のエッセンスは、花田の戦時中の著作『復興期の精神』に発する。
ただこの点は、花田をよほど精密に読みこまないと理解できないから、一般的レベルにおいてはほとんど無効といったほうがいいだろう。教科書風のテーゼが形をなすのは、花田の五〇年代の理論的展開においてだが、これは逆に、言葉がわかりやすすぎて教条的理解しかもたらさないという弊害を生んだ。
足立は、花田理論の影響圏とはべつのところ、「映画=運動」という領域から、原則的にこのテーゼを体現するにいたった。こうした運動者の資質は、『映画/革命』という回顧録をきわめてアクチュアルなドキュメントとして突出させている。
六〇年代文化革命に立ち合った多くの表現者たちへの公正な評価が、ここには大河のように流れている。他者をみる目の暖かさともいえるが、それは個人を捨て花田のいう「インパーソナルな関係」に賭けた人間の、オルガナイザーとしての冷徹さであるように思える。
これは、鈴木清順共闘や批評戦線といった個別のトピックのみではなくて、ほとんど全編に充満しているといってよい。《とにかく、私たちの世代では、平岡と私のように、とん、ちーん、かーんと相互に誤解して合意を発展させていく傾向が強い》とは、じつに含蓄の深い受け止めだ。
足立の現在のポジションは、個人を捨てたところに挫折感は生まれないし、時代が個人を流し去っていくという無力感からも免れることを示しているようにも思える。いまだ闊達に発言する「作家=運動者」にまみえることは奇異なのだろうか。
もちろん、この本を、六〇年代の文化革命がどこまで遠くに達しどこで敗退していったかを測定する現場証言として鑑賞するのは勝手だ。そうした一面から有用でないことはないだろう。
けれどわたしは、ここに記してきた趣旨とは外れるかもしれないが、これを一人の特異な表現者のたどったごくパーソナルな記録として受け取りたい。彼は性と政治が衝突するピンク映画というマイナーな(国内植民地的といってもよい)表現磁場から出立し、パレスチナという「世界性」に投企していった。そこに飛躍断絶はないし、過度に浪漫的な冒険主義もなかったと思える。
真の映像作家となるための長征に旅立ち、そしていくらか変則的な仕方であったが帰還して現在にある、とすれば、この本の過渡性――映画と革命とのあいだに引かれた「/」の意味を埋められるだろうか。
(未発表) 2003.11.20記





