はじまりのないおわり・もしくは映画大通り〈ブールヴァール〉からのパッション [AtBL再録1]
むかしの愛だった。
ゴダールの『パッション』はかれ自身による次の数語に要約できる。
《映画への愛とはユダヤ人たちにとっての約束の大地への愛のような何かだ。それだけだ。ぼくがいいたい唯一のことは、偉大な映画をもてなくなってから、どの国もとてもうまく行ってることだ。エルサルバドルやポーランドのことを考えるとつらくなる。》

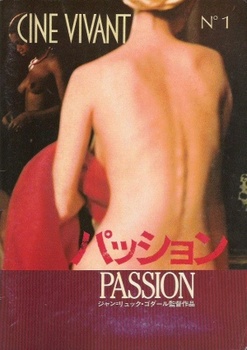
『パッション』は映画への愛が幾重もの屈折を通して、刹那になお輝いてくるような痕跡である。テキストであるといい直そうか。
どこまでもゴダールだ。
愛とは渇望の謂に他ならない。映画への渇望……。
それはまた格別に観客たちを捉えて放さないネガティヴなパッションでもある。
どこまでもゴダールなその途は、必ず、「最低だ!」という自嘲に終る他ない途だ。
涙などは見せない。まさに「最低」なのだから。終り……始まりのない唐突な終り。
それが一九六〇年代の黄昏時、わたしらが大学内バリケードという名付けようもない空間において選び観て取ったゴダールに見透すことの出来なかったものだ。
あるいは、もちろん、見透せていたのかもしれない。
何年か後に、ぶちのめされるような仕方で了解するという形ではあっても……。
そのようにゴダールは時代の一つのコード・ネームではあった。そこにとらわれていたのだった。
何がそんなふうに直接の親近性だったのだろうか。
徹頭徹尾、間接符の中のゴダールの世界。引用符の中に宙吊りになって表出されるゴダールの世界の身悶え。解体意志。
映画をこわすことによってそれへの愛を誓おうとしたあまりにも誠実なゴダール。どういう熱狂にあの頃は包まれていたのだろうか。
新作『パッション』を支えるパッションは、やはり、引用符である。ここで観客は近世絵画の巨匠たちに付き合わされるはめになる。
ゴヤ、ルーベンス、レンブラントたちである。かれらのマスターピースが映画の中で模造されるのであり、おまけにモーツァルトの音楽までが併走させられる。
これはこれで壮大な夢とも云うべきだろうか。
これ自体を取り出していえば、ゴダールはハリウッド式の映画内映画――ジョン・シュレジンジャーの『いなごの日』やエリア・カザンの『ラスト・タイクーン』が記憶に新しい、むしろ業界内幕映画――の大仰な空虚さに近付いたと思える。
だがどこまでもゴダールなこの途は、次のような出自をもっていたことを忘れてはならない。
《映画への愛が手から足にうつり、映画をつくる前に映画を見たことがヌーヴェル・ヴァーグの唯一の運動だ。世界を見るより、映画を観た。……。ぼくたちの間でシネマテークに行くのと、映画をつくることの間に全くちがいはなかった。》
ゴダールが属する映画大陸の大通り〈ブールヴァール〉は「世界」そのものなのだ。
ところで、『パッション』は明瞭な枠組みとしては、映画をつくることについての映画なのである。ゴダールは、映画をつくることに苦闘する同行者たちを、きわめて強引に、そしてきわめて苦渋にみちて、自作の中にひきこんでみせた。ポーランドの「抵抗派」やニュー・ジャーマン・シネマの作家たちは、ゴダールによれば、ヨーロッパ映画共同体の大通りに属する同志だちなのだ。
『大理石の男』『鉄の男』のヒーロー、イェージー・ラジォヴィッチを通してアンジェイ・ワイダが、『マリア・ブラウンの結婚』のヒロイン、ハンナ・シグラを通してライナー・ファスビンダーが、ゴダール映画の人物となるかのように。
狡猾に仕組まれたこれは映画という世界の骨格なのである。
これが解けなくても映画には感応できるが、そこには作家が不在であることも否定できないのだ。
ゴダール、まだ現役だ。
その意味で、『パッション』は、同じ映画をつくることについての映画であるヴィム・ヴェンダースの『ことの次第』の静謐な内省性とは対照的に、小うるさい。
小うるさい限りだ。
「難解・非商業」映画を思い通りつくろうとする作家が資本と衝突する局面をテーマに付随させている二つの映画で、ヴェンダースの指標がアメリカに向けられているのに対して、ゴダールはアメリカには向かず――かれらの映画大陸におけるハリウッド映画という傾向性の歴史と地政を理解する必要がある――どちらかといえば、ポーランドのほうなのか、すでに「連帯」ではなく、半端に思い屈している。
ポーランドのことを考えるとつらくなる、という想いは伝わってきはするのだが。
『パッション』におけるアメリカは、次のように扱われるにすぎない。
緊張にみちた争闘のあげく解雇された監督(ラジォヴィッチ)に、後日、アメリカから買い手がついたとの報が入る。
友人は叫ぶ、スタンバークの光、ボリス・カーロフの光、と。
亡命者たちのハリウッド、である。それをポーランド出身の監督は敢然と拒否する。
『ことの次第』の主人公は、より作者の内面を移入された人物として、最初からアメリカ資本による映画製作を進行中――フリッツ・ラングヘのオマージュの激しさ!――なのだが、ゴダールは自分の映画における監督役をより混沌としたつらさの中に落とし込んでいる。『鉄の男』のヒーロー役者はこの映画においてはまことに精彩を欠くつまらない役柄でしか現われない。
かれが映画の中で何を選び取るのかあまり明瞭ではなく、ゴダールもそれを突き放してしまっているようでもある。
かれは相い変わらず映画から遁走することにおいて映画をつくっている。
遁走? そうではなかったかもしれないが。
映画の中の映画隊は解散される。かれらがどこへ行くのかゴダールは語ることを韜晦している。
語らないのではなく、語れないからそのことだけを呈示するという具合に――。
つらくなるから語れない。
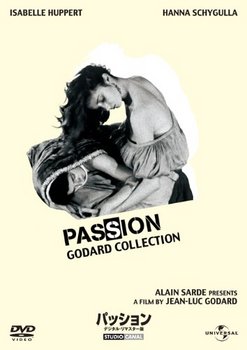
映画大通り〈ブールヴァール〉の愛とは惜別のそれに等しい。
刹那に輝いてくるパッションがそれ故に胸をかきむしるようにせつない。
これが今なお「最低だ!」と自ら目を閉じる破局でなくて何だろうと思いつつ、またしても……。
引用は「パロールヘの道――ゴダール・インタビュー」梅本洋一訳『イメージフォーラム』一九八三年十二月号より)
「詩と思想」25号 1984年3月






コメント 0