アクロス・ザ・ボーダーライン1 [AtBL再録2]


映画は国境〈ボーダー〉に宙吊りにされる。
そのようにしてヴィム・ヴェンダース作品『ハメット』は成り立っている。それはたぶん、書き直されることを欲した一つの原稿に関してのエキセントリックな物語である。
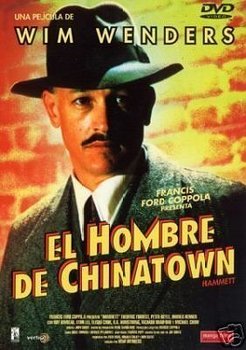
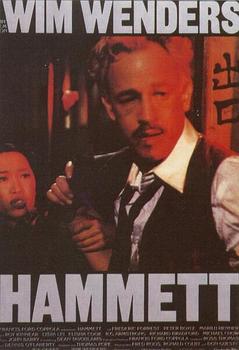
チャイナタウンの銃撃戦のさなか、作家ハメットはブラックマスク誌に送るための原稿を紛失する。かれがその原稿を徹夜でタイプし終ったところに、かれの作品から脱け出してきた旧友の探偵が、かれを事件にまきこむために訪ねてくるのだ。結末について少しばかり不満の残る原稿をかれは封筒に入れて、旧友と街に出かける。
そして喪くしてしまった原稿に再び出くわすのは、すでに深みにはまってしまった事件の頂点においてだった。幕引きにあって事件の当事者たちは口々に、ハメット、あれは仲々の作品だったが、結末については異論がある、とそれを示してみせようとするのだった。
原稿はむろんのこと、それらの混乱の中に再び四散してしまうのだが、やはりついに、作家は自分の手からその作品が紛失されてゆくことに気付くのである。大まかそのように、ヴェンダースは、『ハメット』を映画喪失の物語として提出した。そのように語りかけたかったようである。
それはたぶん、アメリカの土を踏みそこでの製作を宿命付けられたヨーロッパの映画人の宙吊りを示しているのである。映画『ハメット』はそうした回路で固有にヴェンダースに属している。
同様に、原作の小説『ハメット』が固有にジョー・ゴアズに属していることは、ここで強調されるべきだろうか。ゴアズはネオハードボイルド派の平均点的な書き手であり、ヴェトナム復員兵の人物像を模索した『マンハンター』いがい記憶に足る作品もない。そのゴアズの一応の最高作で『ハメット』はある。それは単一にハードボイルド派の始祖へのかれの率直なオマージュによっている。スティーヴン・マーカスが作家論で、ウィリアム・ノーランが文献学で、リリアン・ヘルマンがあまり上等でない伝記作家ぶりで、それぞれ、ハメットを讃えたのと同等の献上がここにある。
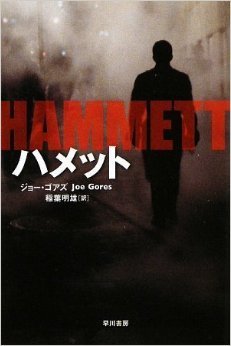

そしてここにも、作家ハメットの「途上の原稿」についての物語が、確かにある。しかしそれは一つの副旋律にすぎないともいえるのであり、書きかけの原稿に関する記述には、常に厳密な伝記的事実への依拠がみられる。
最初の二長編とそのブラックマスク掲載時との異同という初歩的なテキスト・クリティックヘの情熱が――。ただないのは、途上の作品がもつ可能性へのいっしゅ傲慢な無念さ、という一点である。
ひるがえって、ヴェンダースが自分の映画『ハメット』についてもった偏執には、最終的に、無念さというその一点ばかりが残ってきたようなのである。
ヴェンダース作品としては、『ハメット』は、『アメリカの友人』にかなり相似する仕上りになっている。しかしながら、その『アメリカの友人』を観てF・F・コッポラがかれのアメリカの友人になりたいと思ったという「事実」を知っている者にとっては、この結果は、皮肉いがいのなにものでもない。

くりかえすが、ゴアズの原作は、後代からの始祖へのオマージュという主調音を除くと、やはりネオハードボイルドの平均点である。ということはつまり、ロジャー・コーマンの「ファミリー」であるコッポラ・マフィアが手軽にB級作品に仕上げることのできるネタであったにすぎない。
ところがコッポラは、かれの仲間ジョン・ミリアスやジョージ・ルーカスを信じる替わりに、ヨーロッパの作家がアメリカン・ハードボイルドをいかに異化するかの興味に技企することを選んだ。
かれは、例えば、イギリス人トニー・リチャードソンの『ボーダー』がどれだけ俗悪な映画か見届けることができなかったのかもしれない(『ワイルドバンチ』のウォロン・グリーンがシナリオに参加しているにもかかわらず、『ボーダー』は、二十年来の定型を保守した犯罪的な凡作であり、ただライ・クーダーの主題曲だけに価値があった)。
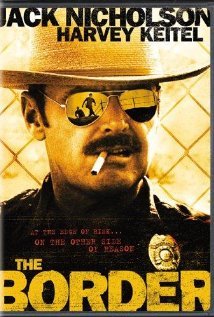
初めにニコラス・ローグが招かれた、ということである。思わせぶりな色彩技巧派であるローグならあるいは、コッポラの望むとおりの異化(イカかタコか知らないが)を、やってのけたのかもしれない。しかし要するに『ハメット』においては回答は明白だったのではないか。ミリアスの『デリンジャー』のハッピネス、ルーカスの『アメリカン・グラフィティ』のノスタルジア、それにプラスして、コーマンの『ブラディ・ママ』のB級の香りをつければよかった。
それ以外になかったのではないか。そのくらいはコッポラ映画マフィアにとっては簡単なコースにすぎなかったのではないか。それをかれはしなかった。コッポラからローグヘ、ヴェンダースヘ、そしてコッポラのヴェンダースからヴェンダース自身へ……。
事態はそのように展開していった。そうである。そのようにしか展開しえなかった。
確かにヴェンダースの『ハメット』には実在した主人公への尊敬はかけらもない。キャラクターにしても、ただ見事に化けたフレデリック・フォレストのハメットもどきが悠々と一人歩きしているのみである。
例えば、他にもハメット役者がいるのなら、『拳銃の報酬』の頃のロパート・ライアンが最適だったとか、様々に想像をかきたててもくれるハマリ役である。しかしかれの友人――われわれがあのコンティネンタル・オプのモデルとして知っているところの探偵――役にいたってはひどいものである。もちろん、原作に濃厚なこの実在のモデルヘの脈々たる敬意から、再び、映画が無縁であるにしても、役柄じたい全く精彩を欠いている。
最初にリチャード・ウイドマークが求められたが実現しなかったことがその主要な理由であるだろうか。『情無用の街』のマシンガン・ギャングから『ニュールンベルグ裁判』の戦勝国検事や『刑事マディガン』のB級刑事まで、多彩なキャリアに輝く大スター、ディック・ウイドマークの探偵役に、ヴェンダースがどんなイメージを抱いたかよく了解しえないが、いずれにしろ、映画の友人役は全くつまらない結果になっている。
少なくとも作家ハメットはこの友人を自作のヒーローとしていたのだし、この理想化が原作から映画の過程で変容したにしても、紛失した原稿の中の重要な役どころであった友人のキャラクターが生きてこないことは、映画の小さくないマイナス面の一つだった。
ことほどさように、『ハメット』は一点を除いては、キャラクターの映画であることをやめているのである。一貫して、紛失した原稿についての物語なのであり、それをタイプライターヘのいっしゅマニアックなまなざしによって、主役はタイプライターかと錯覚するほどに、貫いているのである。
一点を除いて、とは当然ながら、バイプレーヤー選びにおいて固執されたヴェンダースのヴェンダース映画ぶりのことに他ならない。この一点では、まさにキャラクター満載、なのである。エリッシャ・クック・Jrを始めとして、ジョン・フォード映画のスタンプのようなハンク・ウォーデン、そしてシルヴィア・シドニー……。

エリッシャ・クックは元IWW闘士のタクシー・ドライバーとしてかなり重要な役をあてられているのみならず、明らかにハワード・ホークス作品『三つ数えろ』でのかれが殺されるシーンが引用される場面の直後、年代ものの四十五口径を引き抜く見せ場まであたえられているのである。
そしてシルヴィア・シドニーの登場によって、初めてしかも唯一、ヨーロッパ人によるアメリカン・ハードボイルドの異化というコッポラ的モチーフを満足させる場面が、垣間見られたように思う。
フリッツ・ラング作品『暗黒街の弾痕』について、ジェームズ・ボールドウインは、疎外された人間の苦悩をアメリカの白人ならこんなにもありふれた仕方で適確にしかも深く捉えることはできないのだ、と書いたことがある。続いてその主演スターについても、ボールドウインは、シルヴィア・シドニーは自分にニグロ女を想わせるただ一人の白人女優だったし、ヘンリー・フォンダの『怒りの葡萄』での歩き方はかれにニグロの血が混っていることの証明だ、ともいっているのである。
繊細なニグロの小説家は、そのように異化を読み取っていたのである。そして、コッポラに招かれてアメリカにきたとき、ドイツ人ヴェンダースが、第三帝国からハリウッドヘの亡命者フリッツ・ラングにより深く出会った、出会わざるをえなかったことは想像に難くない。

そのようにかれはアメリカ映画を発見したのである。それはかれの映画の宙吊りを示している。それをヴェンダースは、シルヴィア・シドニーを――『暗黒街の弾痕』から約半世紀――登場させることによって、傍点をふったのである。
基本的には、しかしながら、『ハメット』は、紛失した原稿の中の物語が事件の物語を回収するという小味で瀟洒なB級探偵映画に仕上っている。とってつけられた音楽がかきたてる居心地の悪さを我慢すれば、そうした出来映えに満足することができる。
冒頭には、作家が書いている友人を主人公にした短篇の結末のシーンが出てくるわけだ。それは原稿が紛失したまま、映画の時間において脇にどけられているが、終幕になって、事件そのものの展開がその短篇の結末に相似してくることによって前面に出てくる。
そして、事件は、作家の結末を書き変えるふうに落着してしまう。そのとき、作家の探偵稼業は再び作品世界に回収されてきて、見事なゴールを決める。基本的には、『ハメット』はそれ以上の映画ではない。
だがそれを確認すること自体は大よそ無意味なことにすぎない。
ヴェンダース・フィルム『ハメット』について、受け取るべきは、タイプライターヘの視線、アメリカ映画への異化、という二点の強調だろう。
(もうひとつ中国人を扱っての外在的表現の限界性については省略する。ゴアズの原作では魅惑的だった中国女が映画の中で生きてこないのは単なるミス・キャストに起因するだけだろうか。要するに、チャイニーズ・マフィアと警察の骨肉の抗争を描いたマイケル・チミノ作品『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』にしてもそうだが、東洋人は了解不能につき物語世界から排除しておきたいというかつての探偵小説の暗黙の約束事を否定しさるほどには、中国人を対象化できていないのである。こうしたアメリカ映画の地方性についてはまた別の論点があると思うので省略したい。)
かくして映画は国境に宙吊りされる。
結局、更に、ヴェンダースは『ことの次第』をつくって、自己の映画喪失について脚註的に語らねばならなかった。この作品は、単に脚註的なものであるほど貧しいものではないが、あるインタビューでかれは、映画についての痛みはもはや語りたくはない、といっていたのである。
そのようにして、『パリ、テキサス』がつくられたことを、すでに充分に、われわれは知っているのである。どうしてこの作品を支持しないなどということができようか。
再び、これは、具体的に「パリーテキサス」のボーダーに宙吊りにされた意識の物語といえるのかもしれない。
『パリ、テキサス』は映画の獲得である。もし『ハメット』を映画の喪失であると、どうしても呼びたいのなら――。
ヴェンダースはここに至って、自分を〈最後のアメリカ映画作家〉と規定する。だがこれも、国境に宙吊りされた自己意識を定義するための別のいい方にすぎないようでもある。二時間半に及ぶこの豊かな映画のちょうど中程に、唐突に挿入されるシーンは、十六本のフリーウェイが交叉する高架に建てられた陸橋の上で、世界の終末を叫ぶ男をロング・ショットに捉える。男は現代の予言者なのかそれともありふれた気狂いなのか、一切の説明は省かれている。
男は叫ぶ――。
――生まれたままの裸の心できくがいい。約束する。わたしは母の首に誓って約束する。行く所はない。神の見すてたこの谷間にはどこにも行く所はない。呪われたモハベ砂漠からテアズ渓谷を越え、アリゾナに到るどの地域にも、どこにも安全な場所はない。断じていう。安全な場所はない。境界のない国はない。安楽の地などどこにもない。わたしは諸君に警告した。警告しなかったなどとはいわせない。
ヨーロッパで育とうが、どこで生を享けようが、作家は最終最後のアメリカ映画をつくることを宿命付けられている、と。そこまでヴェンダースは辿り着いてしまっているようである。
つづく









コメント 0