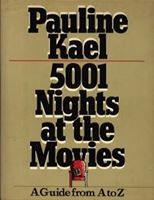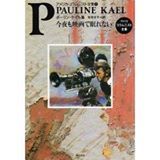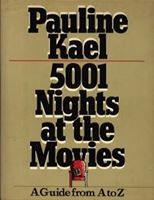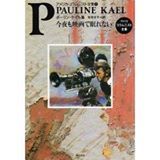『北米探偵小説論』注釈 映画を探して14 2004.01.15の日誌より
ポーリン・ケイルの映画評論集『明かりが消えて映画がはじまる』(山田宏一監修、畑中佳樹、柴田元幸、斉藤英治、武藤康史訳 草思社)を読む。
嬉しくなる本だ。
邦訳されたケイルの本『今夜も映画で眠れない』『映画辛口案内』は読んでいたはずだが、辛辣な寸評の光る一言居士といった印象が強く、いちおうは目を通しておく以上には進まなかった。初めてこの批評家の本領にふれた。
ここには、七十年代なかばに公開された作品への比較的長い作品論が収められている。長さもあって論旨は委曲つくされたものだ。できうるかぎりの精度で作品を観、優れたところ劣ったところを公正に指摘する。映画批評のあり方の正統を行く作法だ。取り上げられた作品のすべてが、わたしが二十代で観たものなのでいっそう引きこまれた。かつて感じ取った熱狂や戸惑いやあるいは不満の数かずが、何によるものだったか改めて犀利に教えられた。自分では言葉になしえなかった感想が簡明に掘り下げられていることに驚く。当時の自分の映画の観方の幼稚さを諄々と説かれる思いだ。
ケイルの最もたる魅力は、いさぎよい断言にある。寸鉄人をさす、という警句がほうぼうに散りばめられていて快い。
たとえば《映画史の不幸とは、壮大な失敗作がつくられることではなく、それがつくられないことなのだ》
これはベルトリッチ『1900年』論のマクラ。ケイルは、この映画の《マカロニ・ウェスタン版階級闘争》の語り口をからかい、《階級闘争も結局のところ二人の少年の男らしさの競争、ペニスの大きさ比べだったのではないか》と看破する一方で、作者の十九世紀小説的叙事詩の偉大さを精緻にたどっていく。こうしたバランス感覚にすぐれた批評の、前半ならわたしでも書ける。むしろ、後半に偏した感のある(日本人の)ベルトリッチ礼賛(その貧相な歴史観を不問に付すかのような無邪気な映像論)に苛立っていたから、前半のみで済まそうとしたのかもしれない。これはこちらの貧しさだ。
チミノ『ディア・ハンター』を壮大な少年冒険ロマン、スコセッシ『タクシー・ドライバー』を良質のモダン・ホラー映画、デ・パルマ『キャリー』を真っ赤なフィルム・ノワール、と断じる小気味の良さ。また『カスパー・ハウザーの謎』までのヘルツォークを説教好きの映画詩人とする。その根拠も作品にそくして明快である。
たとえばジンネマン『ジュリア』を観たさい、わたしが感じた原作者リリアン・ヘルマンへのほとんど道義的な怒り(つまり彼女はハメット派の最も悪質陰険なエピゴーネンだったわけだ)も、本書のような記述によってより広範な説得力を持つのだと知った。ヘルマンが終生いだいた勧善懲悪の世界観をケイルは決して許していないが、それが帯びた時代性については寛容な了解を示している。ヘルマンの酷薄な人間裁断の断片が、ジェーン・フォンダやヴァネッサ・レッドグレーヴという女優にどう反映され、またそれらが映画という「もう一つの人生」の舞台でどう輝いたか。それを辿っていく批評の手つきのスリリングなこと。
あるいはフォアマン『カッコーの巣の上で』に、わたしはひどく失望しなかったにしても、ケン・キージーの原作への過大な思い入れがあった分、図式的な絵解きを感じてしまった。そこにとどまっていた感想も、本書の分析のように、亡命者フォアマンの作家的狭量さ、六十年代カウンター・カルチャー・ヒーローとしてのキージーのヴィジョン的短命さ、主役を演じたジャック・ニコルスンの演技戦略などから多面的に捕捉される論考を前にすると、当時気づかなかった諸々の意味深さを目のあたりにする想いだった。
またデ・パルマに関するさりげない一行にもまいった。「彼もまた文化革命世代の映画ファンのセンスを買いかぶりすぎた作家の一人だった」というくだり。なるほど、大局的にみれば、買いかぶったことの対価などおそろしく貧しいものでしかなかったわけだ。
もっと早く、もっと身近に読みえていたら、アメリカ映画を観るための指南書として活用できただろう一冊である。